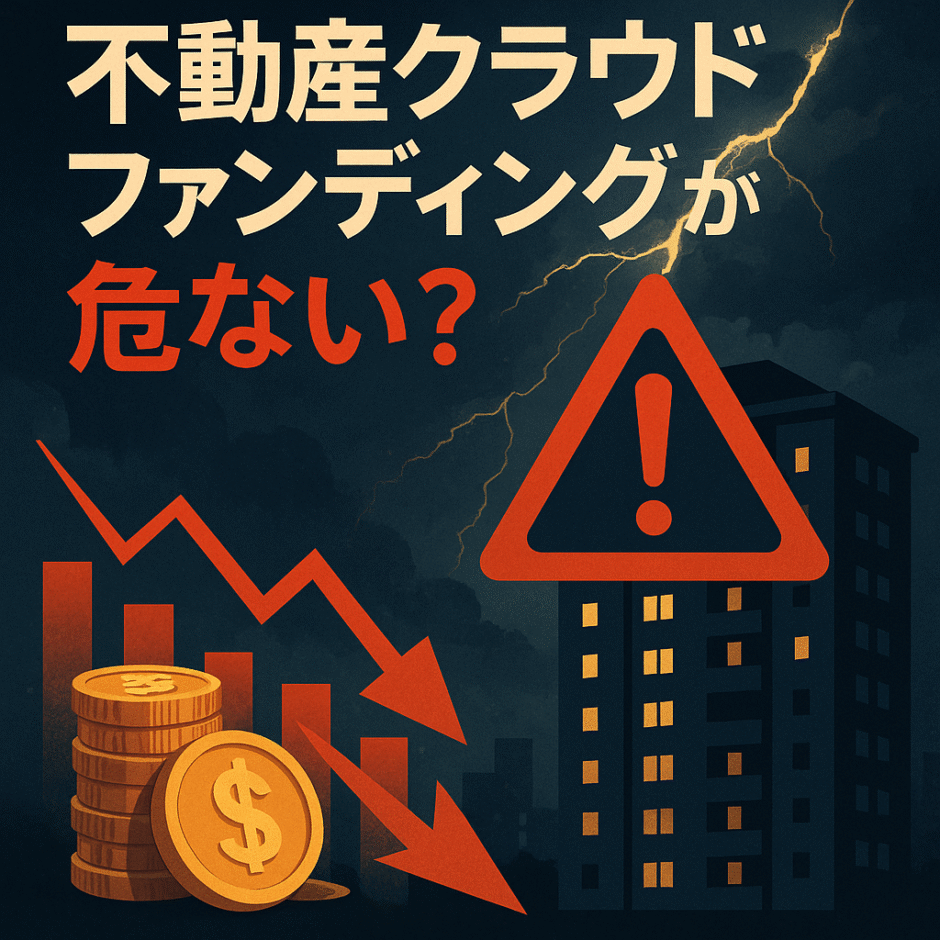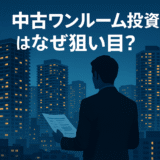1章:不動産クラウドファンディングに何が起きたのか
2025年7月18日、神奈川県に本社を置く不動産クラウドファンディング運営会社「ダイムラー・コーポレーション」が、横浜地方裁判所において破産手続き開始の決定を受けました。
このニュースは、不動産クラウドファンディング業界に衝撃を与えました。理由は単純で、実際に投資家のお金が戻らない可能性が高い事例が現実化したからです。
破産時点で同社が運用していたファンドは合計約1億円規模、想定利回り7〜10%の高利回り案件が中心でした。
投資家は「少額で手軽に不動産投資ができる」との触れ込みで出資していましたが、破産により返済は困難、元本割れの可能性が極めて高い状況です。
さらに深刻なのは、投資家が中途解約できない仕組みにあります。
不動産クラウドファンディングは、通常、運用期間中は元本を引き出すことができません。そのため、投資直後に運営会社が経営難に陥った場合でも、投資家は何もできないままリスクを抱えることになります。
今回の事例では、投資家が6月に出資した直後、7月に破産報道を知るケースが複数ありました。
「資金が拘束されたまま、突然の破産」という最悪の流れが現実化したのです。
これにより、クラウドファンディングの利便性の裏に潜む最大のリスク=運営会社リスクが浮き彫りになりました。

クラファンって、人気だけど、不動産クラファンだけは信用できないね。みんなで大家さんもしかり、実態が不明っていうのが一番無理。リスクコントロールできないからね。私も不動産投資をしてきましたが、このニュースは正直ヒヤッとしました。表向きの利回りだけで安心してはいけないし、“運営会社の体力”まで気にする必要があると改めて痛感しますね。投資は手軽さだけで決めないことが大事です。
2章:なぜクラウドファンディングは「危ない」と言われるのか
不動産クラウドファンディングは、少額から始められ、運用や管理の手間がかからないことから、初心者でも参入しやすい投資手法として人気を集めてきました。
しかし、今回の破産事例をきっかけに、多くの投資家が「思ったよりも危険な投資商品かもしれない」と実感しています。
まず、最大のリスクは元本保証がないことです。
不動産クラウドファンディングは、運用期間中に物件の価格が下落したり、空室が増えたりすると、想定通りの収益が得られず、最悪の場合は元本割れします。一般的な預貯金や国債のような安全性は一切ありません。
まあ投資なので元本保証はないのが当たり前なのですが、例えば自分で不動産を所有していた場合であれば、少なくとも現金化できる・売却できる不動産を持っているわけですからなんとかなります。
ですが今回は物件もない、ただお金がなくなっただけ。
雲散霧消です。
次に、中途解約ができないことも大きなリスクです。
運用期間が6か月〜3年程度のファンドが多く、投資家はその間、資金を引き出すことができません。今回の破産のように、運用中に会社が経営破綻しても、投資家はただ状況を見守るしかないのです。
さらに見落とされがちなのが、運営会社の財務リスクです。
クラウドファンディング事業者の中には、資本が小さく、物件の販売や運営に失敗すると簡単に資金繰りが悪化する会社もあります。投資家は不動産の利回りばかりに目を奪われがちですが、本当に見るべきは運営会社の経営基盤です。
最後に、情報の不透明さも無視できません。
案件の詳細資料では「立地良好」「利回り◯%」といった魅力的な言葉が並びますが、実際には入居率の実績や将来の売却計画が曖昧なケースもあります。運営会社が正直にすべてを開示していなければ、投資家は正しいリスク評価ができません。
これらのリスクが重なると、「少額だから安全」「利回りが高いからお得」という安易な判断が命取りになります。今回の破産事例は、まさにそれを証明する形になりました。

私は投資を選ぶとき、表に出ている利回りよりも“裏側の安全性”を重視します。クラファンは便利ですが、会社の規模や過去の実績、契約の仕組みを見ずに飛びつくのは本当に危険です。投資は、甘い言葉ほど裏に落とし穴があるものですね。
3章:投資で失敗しないためのチェックポイント
不動産クラウドファンディングに投資する際は、表面的な利回りや手軽さだけで判断すると大きな失敗につながります。ここでは、投資家が事前に確認すべき重要なポイントを整理します。
まず一つ目は、運営会社が不動産特定共同事業者として正式に登録されているかどうかです。これは国土交通省や金融庁の登録情報で確認できます。登録されていない事業者は、そもそも法的な保護が受けられず、倒産した場合に資金が戻る見込みは極めて低くなります。
二つ目は、運営会社の財務状況と過去の運用実績です。会社のホームページや決算公告で、資本金、売上高、利益、過去のファンド償還履歴を確認します。短期間で多くの案件を募集しているのに決算内容が貧弱な会社は、資金繰りの悪化リスクが高いといえます。
三つ目は、案件そのものの構造と劣後比率です。クラウドファンディングでは、投資家よりも運営会社が先に損失を負担する「劣後出資」が設定されることがありますが、その比率が低ければ投資家の保護は弱くなります。また、運用期間、立地、入居率の実績、売却戦略も必ず確認する必要があります。
四つ目は、分散投資の徹底です。一つの事業者や一つの案件に資金を集中させると、今回のような破産に直面した際に全損する可能性があります。複数の事業者や物件に小口分散することで、リスクを抑えることができます。
最後に、契約内容を最後まで確認することです。中途解約ができない場合がほとんどなので、生活資金や急ぎで必要になる可能性のあるお金は絶対に投資に回してはいけません。利回りの高さに惑わされず、冷静な資金計画を持つことが欠かせません。

私は投資のとき、まず『最悪のケースでも生活が揺らがないか』を考えます。クラウドファンディングは魅力的に見えますが、結局は不動産投資と同じで、現金化に時間がかかる資産です。生活防衛資金をしっかり残したうえで、小さく試すくらいが安心ですね。
まとめ
2025年に入って実際に起きた不動産クラウドファンディング運営会社の破産は、多くの投資家に衝撃を与えました。
少額から始められて、手間もかからず、高利回りが期待できるという宣伝文句は非常に魅力的ですが、裏側には元本割れや資金拘束、運営会社の経営リスクといった現実が潜んでいます。
今回の事例では、投資家は運用期間中に資金を引き出すことができず、会社の破産を知ったときにはすでに手遅れでした。この流れは、クラウドファンディングの「利便性」の裏にある「構造的な脆弱性」を示しています。
不動産クラウドファンディングは、事業者の信頼性や財務基盤に大きく依存する投資商品です。
高利回りをうたう案件ほど、裏では高いリスクを取っている可能性があります。
投資家が安心して参加するには、事業者の登録状況や過去の償還実績、案件の劣後比率や売却戦略など、数字と仕組みをしっかり確認する必要があります。
また、生活に必要なお金を投資に回すことは避け、分散投資を徹底することが基本です。
最悪のケースを想定し、失っても困らない範囲で投資することが、長く市場に残るための唯一の防御策といえます。

私も副業時代に色々な投資に挑戦しましたが、最終的に残るのは、きちんとリスクを理解して慎重に動いた投資だけでした。クラファンは夢を見せてくれる投資ですが、守りを固めてこそ続けられると思います。今回のニュースは、改めて慎重さの大切さを教えてくれました。
みなさん、浮かれずに地に足のついた地道な不動産投資をしていきましょうね。
それでは最後まで読んでいただきましてありがとうございました!