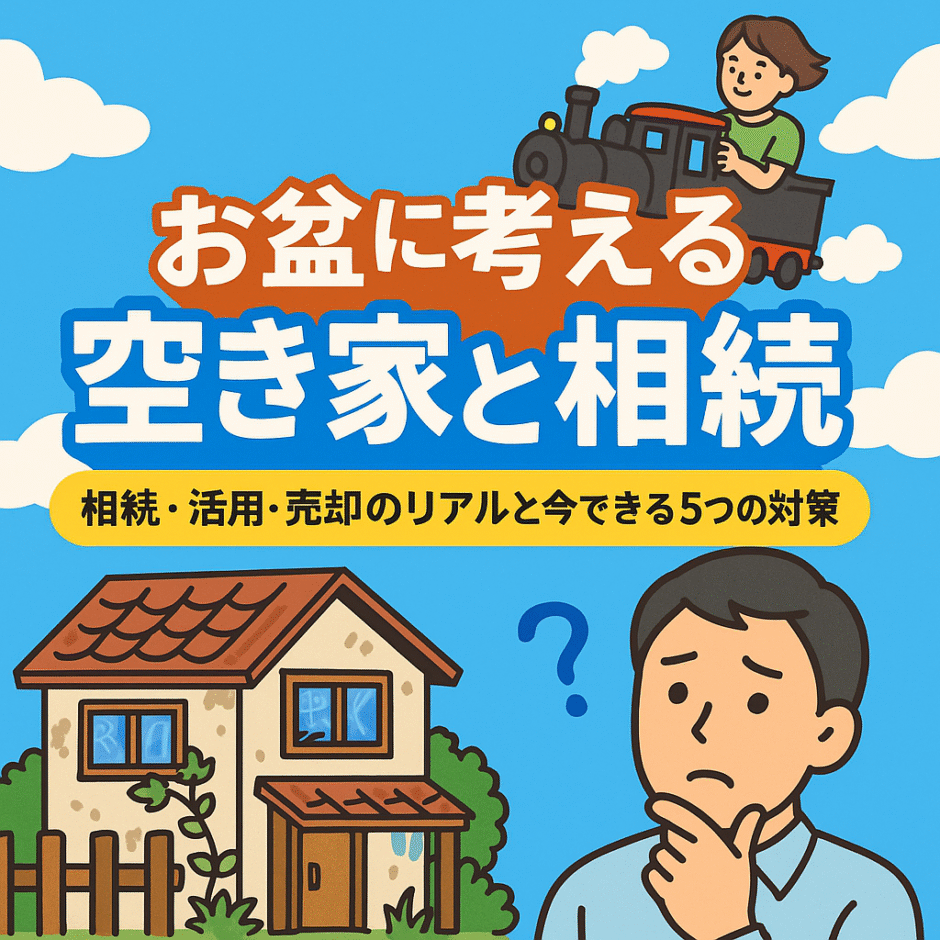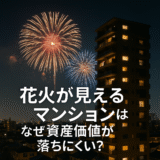はじめに:お盆に帰省して見えてくる、実家の空き家と相続の現実
お盆の帰省は、久しぶりに家族が集まる機会です。年に一度、実家の畳の香り、仏壇の前での手合わせ、親戚の顔ぶれに安心する一方で、ふとした瞬間に「この家、大丈夫かな?」という違和感を抱くことがあります。
玄関のドアが軋み、風通しの悪さにカビ臭さを感じる。庭は雑草に覆われ、仏間の障子には破れが…。かつて笑い声の絶えなかったその家が、今や“空き家予備軍”のように見えてくる。
この“気づき”こそが、お盆がもたらす大きな意味の一つです。ただ懐かしむために帰るのではなく、「この家のこれから」を考えるきっかけをくれる時間なのです。

「実家って“ずっとあるもの”だと思い込んでました。でも、久しぶりに帰ってみたら、あちこちガタが来ていて…。『これ、親が倒れたら誰が管理する?』って、一気に現実に引き戻された感じでした。」
第1章:お盆の帰省は「空き家問題と相続の話し合い」にベストなタイミング
普段の生活では、実家のことを考える余裕はなかなか持てません。都心で働く人にとっては距離的にも心理的にも遠く、兄弟姉妹と顔を合わせる機会も限られています。
しかし、お盆は違います。「帰省すること」が当然の行動として受け入れられているからこそ、構えずに家族が集まることができる。そして、集まった家族でこそ話し合えることがあります。
「実家の今後どうする?」「親がもしもの時は誰が対応する?」といったデリケートな話も、お盆という“非日常の緩やかな空間”の中では不思議と切り出しやすくなります。
もちろん、いきなり結論を出す必要はありません。ただ、“気になっている”ことをシェアする。それだけで、家族の空気が変わり、相続と空き家対策の第一歩が踏み出されるのです。

「お盆って、“地元の空気”が思い出を呼び起こすから、感情的になりがち。でも、逆に言えば“実家の未来”について前向きに考えられるチャンスでもある。あの空気感、やっぱ特別ですね。」
第2章:お盆に明らかになる「放置された実家の空き家リスク」
全国の空き家は、年々増加の一途をたどっています。2023年時点で約900万戸、2030年には1,000万戸を超えるとも言われており、誰もが“空き家問題の当事者”になる可能性を持っています。
お盆に帰省したとき、実家の状態を見て「これはマズい」と感じる人は少なくありません。誰も手入れをしていない庭木が電線にかかり、外壁がひび割れ、雨漏りのシミが天井に広がっている…。
こうした空き家が放置されれば、資産価値は下がるばかりか、倒壊リスク・放火・害虫・不法侵入などのトラブルにもつながりかねません。さらに行政に「特定空家」と認定されると、固定資産税の優遇措置が外れ、税負担は約6倍に跳ね上がるケースもあります。
お盆に気づいた“実家の変化”は、まさに警鐘です。このままにしておけば家も地域も傷む——その現実を、家族で共有することが大切です。

「僕の知り合いは、放置された実家が台風で屋根ごと飛ばされ、補修に200万以上かかりました。しかも誰も住んでない…。この話を聞いて『空き家はリスク資産だ』って本気で思いました。」
第3章:お盆に考えるべき「相続した実家の4つの活用法」
相続後の実家には、住む・貸す・売る・活かす、という4つの選択肢があります。どれが正解というわけではなく、家族構成や地域特性、経済状況によってベストな選択は異なります。
①【住む】:自分で住むことで資産に転換
「住む」という選択は、自分たちの新たな生活拠点にすること。地元へのUターンや親の介護を見据えた引っ越しにもなりますが、勤務地や教育環境、夫婦の意見なども絡むため、簡単には決断できません。
②【貸す】:賃貸収入を得られる。
「貸す」は不動産投資的視点で考える手段。家賃収入は得られるものの、管理・修繕・入居者対応などの実務面が伴います。近隣トラブルへの備えも必要です。空室リスクや管理費用の試算が必要。
③【売る】:現金化して整理できる。思い出や市場価値との折り合いが必要。
「売る」は現金化し、相続の整理をスムーズにする方法です。需要のあるエリアであれば早期売却も可能ですが、思い出との決別や兄弟間の同意形成が鍵になります。
④【活かす】:民泊、シェアハウス、地域活動の拠点など。近年注目されている新しい選択肢。
そして最近増えているのが「活かす」という選択肢。地域に開かれたスペース、こども食堂、シェアハウス、民泊など、社会的な価値を持たせる再活用です。行政やNPOと連携すれば、補助金や地域資源も活かせる可能性があります。ただし、意思統一や調整が最も難しいです。
お盆は、こうした多様な選択肢を家族で検討するきっかけに最適です。

「僕が相談を受けた案件では、“相続した実家を地元NPOに貸して、地域食堂として活用する”という道を選んだ家族がいました。売る・貸す以外にも、“社会に還元する”って道もあるんですよね。」

「ちなみに私はすべてのこどもの【体験格差をなくす】ための非営利型一般社団法人 「親子Mirai Canvas」を運営しております。こどもたちに【夏休みの思い出を無償でプレゼント】する活動をしております。そういった活動拠点のため、空き家などお譲りいただける方がいたらぜひともメッセージいただけますと幸いです!」
第4章:不動産投資家が見る「空き家の実家」を資産に変える視点
一見すると古くてボロボロの実家。でも、不動産投資家の目で見れば、そこには大きな可能性が眠っているかもしれません。
①リノベ
築古物件でも再生可能エリアなら、リノベによる付加価値アップが可能。たとえば、都市部から1時間圏内の駅近であれば、ファミリー向けの賃貸需要が根強いケースもあります。築年数が古くても、フルリノベーションで“デザイナーズ物件”として再生できるかもしれません。
②DIYリフォーム
コストを抑えつつ利回り向上。地方であっても、移住促進や空き家再活用のための行政補助金制度を活用すれば、初期費用を抑えてリスクを軽減できます。空き家バンクや地域おこし協力隊と連携し、コミュニティに貢献するような再生計画を立てれば、社会的信用も得られます。
③地域の補助金(例:空き家再生支援、移住促進制度など)を活用して初期投資を軽減
④トレンドに合わせて「コンセプト民泊」「地域交流スペース」化する戦略も
昨今は小資本からスタートできるモデルも豊富です。お盆に実家を見た時、「売れないから困った」ではなく、「活かせるチャンスがあるかも」と視点を変えてみることが、未来の資産を生むきっかけになるのです。

「空き家をリノベってなんかいいですよね!“地元グルメ”と組み合わせたらヒット!みたいな展開とか楽しそうですね。目の付け所次第で、どこでもチャンスになるんですよね。」
第5章:お盆中にできる「相続準備と空き家対策」の具体的ステップ
実家の空き家問題は、相続と表裏一体です。そして、問題の多くは「準備不足」によって起きています。お盆の滞在中に最低限やっておきたいことは以下の通りです。
・不動産の名義確認
・遺言書や家族信託の検討
・将来の管理者・処分方針の確認
・地元の司法書士や不動産会社への相談準備
まず「名義の確認」。登記上の所有者が亡くなっていないか?すでに自分や兄弟になっていないか?ここを確認するだけでも大きな進歩です。
時間に余裕があれば、「家族信託」や「遺言書」の話も出してみましょう。親が元気な今だからこそできる備えです。
次に「方向性の共有」。売却するのか?貸すのか?誰が中心になるのか?ざっくりでもいいので、家族の温度感を合わせることが重要です。
そのうえで、「専門家に相談する段取り」をとる。司法書士、不動産会社、税理士など、どこに相談すべきかの“連絡先を押さえる”だけでも、後の行動スピードがまったく違います。
お盆という“時間のゆとり”の中で、こうした話をしておくことが、未来のトラブル回避につながります。

「「話しておけばよかった」って声、ほんと多いんです。最初は勇気がいるけど、“いざという時に自分が困らないため”って思えば動けますよ。」
おわりに:お盆だからこそ「空き家」と「相続」を家族の未来につなげる
空き家の問題も、相続の問題も、向き合うにはエネルギーが要ります。でも、放置するほうが、後で何倍もの労力とコストがかかります。
お盆という“立ち止まるタイミング”で、実家と向き合い、家族と話し合うこと。それが、想い出を守りながら未来をデザインする最初の一歩です。
実家は、家族の記憶を刻んできた場所。だけど、これからは「誰かが背負うだけの重荷」ではなく、家族みんなで「未来をどうするか考える資産」に変えていくことができるはずです。
お盆という特別な時期に、ぜひ「家族で話す」「プロに相談する」「情報を調べる」というアクションを取ってみてください。あなたの選択が、家族全員の未来を明るくするかもしれません。

「僕が不動産投資を始めたのも、実家の空き家問題がきっかけでした。すべての家にストーリーがある。それを次の人にどう手渡すか、ってめっちゃ大事だと思ってます。」
それでは最後まで読んでいただきましてありがとうございました!