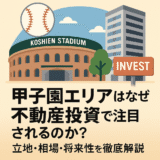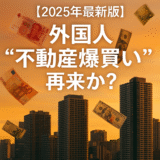実例:カボチャの馬車事件に学ぶシェアハウス投資の落とし穴
2010年代後半、「カボチャの馬車」というブランド名で展開された女性専用シェアハウス事業は、表面利回り8%以上をうたい、主にサラリーマン投資家・CAさん・看護師さんに販売されました。
スルガ銀行によるフルローン・オーバーローンを活用し、自己資金ゼロでも始められることが魅力とされ、多くの契約が成立しました。
しかし、現実には
- 無理のあった家賃保証(サブリース)が破綻
- 入居者募集が想定通り進まず、空室だらけ
- 金融機関への返済が滞る
といった状況に陥り、オーナーが巨額の負債を抱える事態となりました。
その背景には、過剰な建築費・販売価格の設定や、入居需要の甘い見積もり、そして銀行の審査不正があったとされています。
この事件から得られる教訓
- 「家賃保証=安全」ではない
保証会社や運営会社が経営破綻すれば、保証契約も無効化される。むしろ家賃保証は超危険です! - 需要予測は自分で行うべき
販売業者のデータや営業トークだけを鵜呑みにしない。 - 金融機関との契約内容を精査する
返済計画に余裕がなければ、短期間で資金繰りが詰まる。

私もこの事件はよく覚えています。ブランド力や「女性専用」という響きに安心感を抱く人は多かったですが、結局は「運営と需要」が現実に合っていなければ崩れる。シェアハウス投資は特に、この2つを外すと一気に危険ゾーンに入ります。
1章 シェアハウス投資とは?基本の仕組み
シェアハウス投資は、1つの住宅や建物を複数の入居者でシェアし、個室+共用スペースという形態で提供するビジネスモデルです。
一般的な賃貸物件(ワンルームやファミリータイプ)と比べ、同じ建物内で複数契約が発生するため、家賃総額が上がりやすいのが特徴です。
例えば、3LDKのマンションを1世帯に貸す場合の家賃が月12万円だったとします。
しかし、各部屋を個別契約(例:1部屋5万円×3室)で貸せば、月15万円の収入になり、年間で36万円の差額が生まれます。
これに加え、リビングやキッチンは共有とすることで、入居者にとっても家賃負担を抑えつつ広い空間を利用できるメリットがあります。
また、投資対象としては以下の3パターンがあります。
- 一戸建て(中古住宅をリフォームしてシェアハウス化)
- マンション1室(間取りを改造して複数人利用可能に)
- 専用設計の新築シェアハウス

シェアハウスは「安く借りたい人」と「高利回りを狙う投資家」のニーズがピタっと合う形態です。特に中古戸建てをリフォームして始めるパターンは、初期費用を抑えやすく、地方でも成立しやすいですね。
2章 シェアハウス投資のメリット
① 高利回りが期待できる
シェアハウスは1棟から複数契約が生まれるため、同じ建物を通常賃貸で貸すよりも総賃料が高くなる傾向があります。
特に、家賃相場の高い都市部では利回りが10%以上になる事例もあります。
② 空室リスク分散
例えば6部屋あるシェアハウスで1部屋空室になっても、残り5部屋分の家賃収入があります。
ワンルーム投資のように「1室空いたら収入ゼロ」になるリスクが低減します。
③ ターゲットの幅広さ
- 留学生や外国人労働者
- 学生や新社会人
- 転職・転勤で短期滞在する人
- ミニマリストや節約志向の人
といった幅広い層を対象にできるため、需要の波を緩和できます。
④ 改装費用を抑えられる場合がある
中古物件を安く仕入れ、間取り変更や家具・家電の設置で対応できることが多く、大規模な新築投資より初期費用が少なくて済みます。
⑤ 賃料以外の収益も狙える
共用部にコインランドリー、レンタルスペース、シェアオフィス機能を加えることで、家賃以外の副収入を得られる可能性があります。

「高利回り」という言葉は魅力的ですが、私の経験上、実際には運営や募集の工夫があって初めて数字が伸びます。
立地・ターゲット設定・共用部の魅せ方、この3つの掛け算がカギです。
3章 シェアハウス投資のデメリットとリスク(深掘り版)
① 運営の手間
シェアハウスは通常の賃貸よりも入居者数が多いため、管理業務が増えます。
- 共用部の清掃(頻度高め)
- 設備の修繕
- 家具・家電の交換
- 入退去時の手続き
これらを自分でやると負担が大きく、管理委託を使えばコストがかさみます。
② 入居者トラブル
共同生活では生活習慣や価値観の違いから摩擦が起こりやすいです。
- 騒音問題(深夜の音楽・通話)
- 掃除やゴミ出しルールの違反
- 共用部の私物化や破損
これらが放置されると退去が増え、悪評がSNSや口コミで広がるリスクもあります。
③ 法的規制や条例
地域によっては、シェアハウスを「寄宿舎」とみなし、建築基準や用途地域の制限がかかることがあります。
さらに、外国人比率が高い場合は消防・防犯面で追加規制が課されることもあります。
④ 需要変動リスク
ターゲットの需要が急減すると空室が増えます。
例:コロナ禍では外国人留学生の来日制限により、多くのシェアハウスが空室化しました。
⑤ 利回り低下の落とし穴
管理委託費・光熱費・清掃費などの運営コストが予想以上にかかり、想定していた利回りを維持できないケースがあります。

数字上の利回りが良くても、運営実務を甘く見積もると“思ったより儲からない”状態になります。シェアハウスは「物件購入後の管理体制」が利益の大部分を左右します。
4章 シェアハウス投資で成功するためのポイント
① ターゲット層の明確化
- 外国人留学生向け:英語対応、家具付き、短期契約可能
- 女性専用:防犯設備・デザイン性・清潔感重視
- 短期滞在者向け:駅近・契約の柔軟性・光熱費込み
→ 誰をメイン顧客にするかを明確にし、それに合わせた設備・ルール・集客手段を設計します。
② 立地選び
- 駅から徒歩10分以内
- 商業施設やスーパー、病院が近い
- 近隣に大学・専門学校や企業集積がある
- 外国人需要がある観光地・都市部
これらは安定稼働の鍵となります。
③ ルールと契約書の整備
- 共用部の使用ルール(掃除当番・ゴミ出し・騒音対策)
- 光熱費の計算方法(固定or実費)
- 禁止事項(ペット・喫煙など)
これらを契約書に明記し、トラブル予防につなげます。
④ 運営体制の確保
- 自主管理:利回りは高いが時間と労力が必要
- 管理委託:コストはかかるが安定運営可能
→ 投資スタイルに応じて選択
⑤ 内装と清潔感
第一印象で入居率が変わるため、共用部は明るく清潔に保ちます。家具やインテリアも統一感を持たせ、写真映えを意識すると募集が有利になります。

私は立地よりも先に「ターゲット決め」を重視します。なぜなら、ターゲットが決まれば求められる立地条件も明確になるからです。逆にターゲットが曖昧だと、募集時に方向性がブレて苦戦します。
5章 失敗事例と回避策
① 需要調査不足による空室長期化
ある投資家は地方都市の中古戸建てを格安で購入し、6部屋のシェアハウスとして改装しました。
しかし周辺には大学も大企業もなく、交通アクセスも不便だったため、募集から半年経っても3部屋しか埋まらず、利回りは想定の半分以下に。
回避策:投資前に「エリア内の賃貸需要調査」を徹底する。ポータルサイトの空室状況、同業物件の稼働率、周辺の人口動態などを確認する。
② ルール不備による入居者トラブル
別の事例では、契約書に共用部利用ルールがほとんど明記されず、ゴミ出しや掃除を巡って入居者間の揉め事が頻発。
結果として退去者が続き、悪い口コミが広がった。
回避策:契約時に利用規約を明確にし、特に共用スペースの清掃方法、静粛時間、来客ルールを細かく設定する。
初回入居時に説明会を行うと効果的。
③ 過剰なリフォーム費用
「おしゃれな内装にすれば埋まる」と考え、1000万円以上かけてリノベーションした投資家もいますが、家賃設定を高くせざるを得ず、ターゲット層に合わず空室が続く結果に。
回避策:内装はターゲット層に合わせてコストを最適化。
高級感よりも清潔感・機能性を優先し、費用対効果を意識する。
④ 法的規制の見落とし
一部のエリアではシェアハウスが「寄宿舎」扱いとなり、防火設備や避難経路の基準が厳格化されます。
これを知らずに運営開始し、後から高額な改修費用を負担するケースもあります。
回避策:購入前に役所の建築指導課や消防署に確認し、用途変更や必要な設備要件を把握しておく。
⑤ 管理体制の不備
自主管理でコストを抑えようとしたものの、入居者対応や清掃、設備修理に時間を取られ、本業や生活に支障が出た事例もあります。
回避策:物件規模や自身の時間的余裕に応じて、管理委託の利用や清掃業者の契約を検討する。

失敗している人の多くは「利回りの数字」だけで飛びついています。私は物件を見るとき、必ずそのエリアの競合物件を見学し、ターゲット層と合致するかを肌で確かめます。数字よりも“現場感”が大事です。
まとめ
シェアハウス投資は、複数契約による高利回りと空室リスクの分散という大きな魅力があります。特に都市部や特定のターゲット層(外国人留学生、女性専用、短期滞在者など)に向けた戦略がはまれば、安定したキャッシュフローを生み出せます。
一方で、成功するには「数字の利回り」よりも「運営の現実」を重視する必要があります。入居者同士の人間関係、共用部の管理、法規制への対応など、通常の賃貸経営よりも気を配るべきポイントが多いからです。
2025年現在、物価高や住居コスト上昇によって、「一人暮らしは厳しいけれど、完全な同居は避けたい」という層の需要が伸びています。
この潮流はシェアハウスにとって追い風ですが、同時に競合も増加しているため、差別化と運営力が勝敗を分けます。
これから参入を考える方への提言
- ターゲットを絞る(万人受けを狙わない)
- 現地・競合の徹底調査(数字だけでなく、現場の雰囲気を確認)
- ルール設計と契約内容の明確化(トラブル防止の要)
- 管理体制の確保(自分が関われる時間を正直に計算)
- 初期投資の費用対効果を意識(豪華さよりも清潔感と機能性)
これらを押さえれば、シェアハウス投資は不動産ポートフォリオの中でも非常に強力な収益源になり得ます。

私の経験上、シェアハウス投資は「人と人をつなぐ事業」でもあります。数字や利回りだけでは測れない、入居者の生活満足度がそのまま経営の安定につながります。物件だけでなく、そこに暮らす人々の生活をどうデザインするか——そこにこそ面白さがあります。
さらに、私はシングルマザー・ファザーを応援する一般社団法人を運営しているため、ゆくゆくはそういったご家庭に提供できる居場所としてシェアハウスを運営したいですね。
一緒にやってくださる方募集!笑
それでは最後まで読んでいただきましてありがとうございました!